「リスクマネジメント講座」(指導資格者むけ) 2025年度版 危険予知編
リスクマネジメント講座資料・危険予知編(2025年度版)
リスクマネジメント講座資料・危険予知編(2025年度版)を始めます。
「次へ」をクリックして講習を始めてください。
危険予知のトレーニング
- リスクマネジメントには「想像と準備」の徹底が重要です。
「まぁ、いいや」「この位大丈夫だろう」と思うところに将来大きな事故・怪我につながるような危険が潜んでいます。何らかの予兆(サイン)を感じたら、速やかに対応しましょう。
また、人は「危険な事態には陥らないだろう」「大したことにはならないだろう」「自分は大丈夫だろう」と、危機に直面しても認めようとしない面があります。
日頃に「想像:事故の予期」と「準備:事故の回避と事故後の対応」を訓練し、万が一の事態のときに、当たり前に「命を守ること」(一次救命措置)が実施できるようにトレーニングをしましょう。
また、リスクマネジメントの取り組みを、一時的なものではなく、毎回毎回の稽古で、毎週毎週に続けていくことが必須です。 - あなたの道場・教室での稽古にはどのような危険があるか「想像」してください。
- その危険に対して、どのような「準備」が必要ですか。答えは1つだけではありません。
- 様々なケースを想像し、準備をしましょう。
「命を守ること」の本会での実例
- これはある教室で実際に起こったことです。
ある日の稽古で、いつもどおりに稽古をしていたところ、突然、一人の方が倒れてしまいました。あなたならどうしますか。 - その教室の指導者は、一緒に稽古をしていた方と連携し、救急車を要請、AEDを用いて、速やかに一次救命措置を行いました。
その後、救急車が到着、その方は病院に搬送されました。数日間の入院は要したものの、大きな後遺障害もなく退院なさいました。 - 日頃のリスクマネジメント、一次救命措置の訓練により万が一の場合に命が守られた実例です。
リスクマネジメントにおける最優先事項は「命を守ること」
- 必要があれば迷わず救急車を要請しましょう。会員の生命を守るのが最優先事項です。
総務省消防庁の令和5年度データでは、全国の救急車の現場到着は平均10.0分(前年度10.3分)、病院到着は45.6分(47.2分)です。 - 119番通報をして救急車の到着を待っていたのでは7.3%の人しか救命できません。
一般市民が傷病者に「心肺蘇生を実施した場合」は、しなかった場合の1か月後生存者数は約2.0倍、うち1か月後社会復帰者数は約2.9倍です。さらにAEDを用いた電気ショックが行われることで、突然の心停止の約半数の人を救えます。
ここから見ても、日頃のリスクマネジメント、一次救命措置の訓練の重要性をご理解いただけると思います。
参考資料:総務省消防庁「令和6年版救急救助の現況」の公表(報道資料)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000991299.pdf - 万が一の事態の際、適切な医療を受けるまで、目の前の方の命を守れるのは私たちです。
勇気をもって、一次救命措置を行い、速やかに適切な医療を受けられるように日頃のリスクマネジメント、一次救命措置の練習などで万が一の場合に備えましょう
教材動画:総務省消防庁「一般市民向け応急手当WEB講習 普通救命講習編」
応急手当WEB講習 (fdma.go.jp)
設問:稽古前のチェックポイントは?
解答例:
・室温湿度の調整、畳(マット)の隙間がないか、道場内は整理整頓されているか、など
・初期対応マニュアルは常備されているか、救急セットはあるか、AEDは近くにあるか、など
・会員の様子を確認→いつもと違和感がないか(必要なら声掛けなど)
顔色、表情、目線や目つき、挨拶や返事、話し方、行動、道着の着方など
特に子ども会員は、はしゃぐ、さわぐ、うずくまる、ポツンなど稽古に向けての態度は大丈夫か、
など
設問:夏季に限らず、高温多湿が予想される日の稽古は?
解答例:
・熱中症予防のため、中止や延期の検討、など
・エアコンの使用、適宜全体で休憩する、それ以外に各自が休憩できるように周知、など
・体調や表情に何か変化があったら→大人が付き添う、救急車の要請、#7119へ問い合わせ、など
設問:初心者が稽古をする際の危険にはどのようなものがありますか?
解答例:
・稽古に不慣れ→十分に柔軟体操、受身の稽古をする、など
・受身に不慣れ→技の中でいつ、どのように受身を取るか指導する、など
・技に不慣れ→はじめはゆっくり稽古、慣れてきたらスムーズにできるように、など
・前受身が心配→技は投げる手前までの稽古にする、後受身に慣れてから前受身を始める、など
設問:剣・杖・短刀などの武器を用いた稽古の危険にはどのようなものがありますか?
解答例:
・剣・杖・短刀を振りかぶる時→周囲の方に配慮、同じ向きで、適切な間合いで、交代で、など
・武器取りの稽古の際、掛かる時、技の途中、取り上げる時など→周囲の方に配慮、など
設問:大勢の会員が稽古をする際の危険にはどのようなものがありますか?
解答例:
・周囲の人とぶつかる→技を行う向き(受身の向き)、投げ受けの間合い、組と組の間合いに配慮、稽古内容を見直す、稽古方法を見直す(掛かり稽古に、技の一部のみの稽古に)、など
・上手く稽古できない人、技ができない人が埋もれる→グループ別、先輩がつく、など
設問:中高年の会員が稽古をする際の危険にはどのようなものがありますか?
解答例:
・過度な運動量、急激に変化する動き、長時間立ったまま(坐ったまま)、過度な緊張が続く
→適宜休憩をとる、ゆっくりやる、無理をさせない、など
設問:子どもクラスで稽古をする際の危険にはどのようなものがありますか?
解答例:
・ふざけている子→落ち着く時間を作ってから稽古(稽古前・稽古中も適宜)、など
・慣れていない子→技の一部から稽古(できることを増やす)、など
・年齢差、身長差、上達度の違い→組み合わせを工夫、稽古内容の工夫、など
設問:子どもクラス会員が帰宅途中で保護者と行き違いになりました。どうしますか?
解答例:
・保護者に連絡、子どもを探す、道場教室で誰かが待機(戻ってくるかも)、など
・そもそも引き渡し方法を確認、など
設問:会員が足指を痛めました。どうしますか?
解答例:
・救急車の要請、#7119へ問い合わせ、近隣の救急病院に送る、など
・医療機関への受診をすすめ着替えて帰宅させる、など
※ケガの程度(打ち身、捻挫、骨折など)は医師以外では判断できません。
ケガをした会員(保護者)と相談の上、適切な医療を受けるようにお勧めください。
※本会での事例:稽古中、受身の際につまずいて痛めた。
→その後は稽古せず、冷やして安静にして、稽古終了後に整形外科を受診したところ足指を骨折していた。2ヶ月程稽古を休み、その後に復帰した。
スポーツ安全保険を利用して治療費に充当した。
設問:会員が肩を痛めました。どうしますか?
解答例:
・救急車の要請、#7119へ問い合わせ、近隣の救急病院に送る、など
・医療機関への受診をすすめ着替えて帰宅させる、など
※ケガの程度(打ち身、捻挫、骨折など)は医師以外では判断できません。
ケガをした会員(保護者)と相談の上、適切な医療を受けるようにお勧めください。
※本会での事例:稽古中、前受身の際に肩から落ちて痛めた。
→その後は稽古せず、冷やして安静にして、稽古終了後に整形外科を受診したところ鎖骨を骨折していた。その後に手術を受け、2ヶ月程稽古を休み、復帰した。
スポーツ安全保険を利用して治療費に充当した。
設問:会員が頭部を打ちました。どうしますか?
解答例:
※特に頭部を打った(強打ではなくても)場合、重大事故に至る可能性があります。
・速やかに救急車の要請、#7119へ問い合わせ、救急病院(脳神経科のあるところ)に送る、など
・保護者や家族連絡をする、など
※ケガの程度(打ち身、捻挫、骨折など)は医師以外では判断できません。
ケガをした会員(保護者)と相談の上、適切な医療を受けるようにお勧めください。
※本会での事例:稽古中、つまづいて前に倒れ、畳と床の段差に額をぶつけ出血。
(眉毛上が深さ数ミリ程度パックリ切れた)。
→意識があり、受け応えに異常は感じなかったが、頭部の怪我であり、まずは#7119に連絡。
当人へのいくつかの質問(意識、話し方、見え方、ケガの程度など)のあと、近隣の脳神経外科のある救急病院の紹介を受け乗用車で送る(この事例では救急車ではなくて良いと指示があった)。
その間も清潔な布で患部を強く抑え止血。出血は止まった。
紹介を受けた病院数件に電話連絡をしたが、急患で一杯で、やっと受け入れ先が決まり、病院でもしばらく順番待ちになった。頭部の検査を受けたが異常なし、患部を縫合され帰宅。2週間後に再検査、幸い異常なしで稽古に復帰。
スポーツ安全保険を利用して治療費に充当した。
設問:大規模災害が稽古前/稽古中/稽古後に起きました。どうしますか?
解答例:
・速やかに稽古は中止、安全なところに移動する、など
・「初期対応マニュアル」に基づき避難先に移動か、道場教室で待機かの判断、など
・避難先を道場前に掲示、会員、保護者に引き取りの連絡、など
※本会での事例:(2011年3月の東日本大震災の際の宮城県内のある道場)
・震災時、稽古中ではなく道場には誰もおらず人的損害なし。内陸部のため津波の影響はなかったが、棚が倒れるなど一部物損あり、数日間、電話は不通、電気・ガス・水道もストップ。
・後日、一斉メールで当面は稽古なしの連絡、会員の安否確認、道場は約3週間休止し、4月より再開。
設問:大雨警報が稽古前/稽古中/稽古後に発令されました。どうしますか?
解答例:
・速やかに稽古は中止、安全なところに移動する、など
・「初期対応マニュアル」に基づき避難先に移動か、道場教室で待機かの判断、など
・避難先を道場前に掲示、会員、保護者に引き取りの連絡、など
危険予知のトレーニングのまとめ
・まだまだ予測できる危険があります。
・危険予知のトレーニングは指導者中心に、大人会員、保護者と機会を作り、道場教室全体での取り組みにしていきましょう。
・全ての指導者がこれら全ての内容を熟知して実践することはもちろんですが、日々の稽古でのリスクを低減するためには、会員一人一人や保護者の理解と協力が必要です。
特に稽古の際に生じうる危険については、指導の現場で都度、注意喚起するなどして会員同士が安全に稽古できるよう指導してください。
・みなさんとご一緒に、安心、安全に心身統一合氣道の稽古をして、益々「氣」が出る道場教室づくりをして参りましょう。
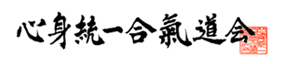 Members Site
Members Site